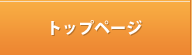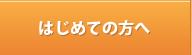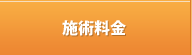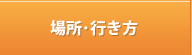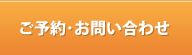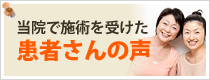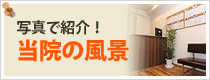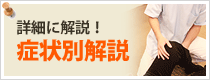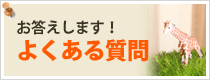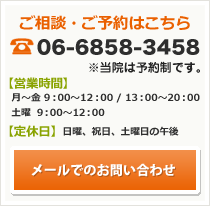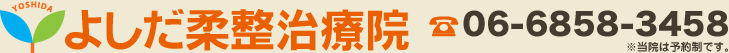脊柱管狭窄症の症状でお悩みの人の話を聞いていると
「私は症状や痛む場所が日によってコロコロ移動したり変化するんですが、こういった事って異常な事なんでしょうか?」
といった質問をよくいただきます。
このように脊柱管狭窄症の症状や痛む場所が移動したり変化する事は、実はそこまで珍しい話ではありません。
そこでこのページでは、脊柱管狭窄症の症状や痛む場所が移動したり変化する理由について説明させていただきます。
ちなみに私は医療系の国家資格である柔道整復師という資格を持っている人間です(ここをクリックすると私の柔道整復師免許証の写真が出ます)
医療系の国家資格を持っている人間の端くれとして、出来るだけ丁寧で分かりやすい説明を心がけていますので、こういった事に興味のある人は是非参考にして下さいね。
スポンサーリンク
脊柱管狭窄症の症状や痛む場所が頻繁に移動する理由
早速痛む場所がころころ移動したり変化する理由について説明させていただきますね。
少し難しい話になってしまうかも知れませんが、人の痛みというものは脳がつくっている一つの感覚です。
脳は体のあちこちから色んな情報を集めてその体の悪い所を探っており、ある一定以上の負担がかかっていると脳が判断した時にその箇所に痛みを発生させます。
脳が痛みを発生させる理由は一種の危険信号みたいなものだと思ってください。
例えば腰に痛みが発生しているという事は
「腰が悪くなっているよー気をつけてよー」
と脳が知らせてくれているわけです(迷惑な話ですが)
そして、脳が痛みとして危険信号を出す時には優先順位が存在します。
その時その人の体の中で、最も悪い所を優先的に痛みを強調させるという優先順位です。
こういった「痛み」のメカニズムを踏まえた上で、脊柱管狭窄症の痛みが移動したり変化する事について説明していきたいと思います。
「痛み」という危険信号には、その時最も悪い場所の痛みを優先的に強調するような特徴があります。
例えば右腰に痛みが集中している場合、右腰に関連する部分が最も悪いという事になります。
そしてその右腰の痛みが消えるか軽減して、今度は左腰の痛みが出てきたとします。
その場合は、右腰よりも左腰の方が悪いと脳は判断しているという事です。
つまり、痛む場所がころころ移動したり変化するという事は、割と広範囲に悪い所が存在しているという事であり、脳はその中の特に悪い所しか痛みを強調しないため、その日その時に負担が集中する箇所によって、脳が痛覚を感じさせる優先順位が変わってしまうため発生しているんです。
そしてご存知の人も多いと思いますが、脊柱管狭窄症とは神経が通っている脊柱管の変形によって中の神経を圧迫してしまい発生する疾患です。
圧迫された神経によって痛む場所は大きく異なりますが、その神経が支配している領域のどこに症状が発生してもおかしくないため、脊柱管狭窄症は非常に広範囲に症状を発生させる疾患でもあるんです。
(首や背中、腕や手、腰や下半身など全身に症状が発生してもおかしくありません)
症状や痛みの発生している場所が他の疾患に比べても多い事から、その日その時の状態によって脳が優先順位をつけて痛む場所は移動したり変化しやすい疾患とも言えます。
スポンサーリンク
脊柱管狭窄症の治療後に痛む場所が変化する事は悪い反応ではない事も多い
痛む場所が移動したり変化する事は、脳の機能によって痛覚を発生させる場所に優先順位をつけているという説明を上記で説明させていただきました。
実はこういった反応は、脊柱管狭窄症の治療後に発生する事が多い反応でもあります。
例えば右足に痛みが発生している患者さんがいるとします。
病院などで治療を受けた後に、右足の痛みが消えたけど、今まで感じなかった背中の痛みやお尻の痛みが発生したらみなさんはどう思いますか?
あまり良くないんじゃないか?と思う事も多いと思います。
しかし、これは元々悪かった箇所(右足)が改善したため、脳はその次に悪い箇所の痛みを強調しているためこういった反応が発生しているんです。
つまり治る過程の反応としては決して悪くないんですね。
(元々悪かった場所が改善しているから違う場所の痛みを感じるようになった訳ですから)
こういった反応は本当に頻繁に起こります。
右肩を治療して楽になれば、今まで感じていなかった左肩の痛みが発生したり、肩こりが改善したら今まで感じなかった膝の痛みが発生したり、本当に面白いほど脳はその時その時に悪い所を優先して痛みを発生させるように作られています。
そのため、もし治療後などに痛む場所が移動したり変化した場合は、決して悪い反応じゃない可能性が高いため、あまり心配しすぎないようにしてくださいね。
脊柱管狭窄症から発生している症状なのであれば、弱い刺激で行う治療が効果的
ここまでは、脊柱管狭窄症の症状た痛みの場所が移動したり変化する理由について説明させていただきました。
上記でも説明したように、治療後に痛む場所が変化する事は良い反応である事も多いんです。
ただし、痛む場所が移動したり変化しても痛みがより強くなっている時は気をつけて下さいね。
その場合は単純に悪化している可能性もありますので。
特にマッサージなどの治療は脊柱管狭窄症との相性はあまり良くありません。
脊柱管狭窄症のように、背骨の骨や軟骨の変形などが症状に大きく関わっている場合、その周辺には常に強い炎症が発生しています。
炎症は近くの神経を興奮させて、感覚を過敏にさせる特徴を持っています。
感覚が過敏になると、簡単に言えば少しの負担やちょっとした動作でも痛みを感じやすくなってしまうんです。
つまり、こういった症状の方にマッサージやバキボキするような、比較的強い刺激で行う治療を行うと、あまり効果がない所か逆効果になってしまう可能性があるんですね。
どこの治療院やマッサージに通っても改善しなかったという人は多いと思いますが、そのほとんどの治療が割と刺激量の多い治療である事が多いと思います。(そちらの方が患者ウケは良いと思いますので)
逆に、優しく弱い刺激で行う治療であれば、治療行為が負担になりませんので改善する可能性があります。
脊柱管狭窄症のように、骨や軟骨の変形や神経の圧迫が痛みに大きく関わっていたとしても、その症状には筋肉の緊張状態や炎症の有無も痛みにはかなりの部分で関わっています。
強い刺激で行う治療では、強い炎症による過敏性が邪魔をして改善する可能性は低いと思いますが、弱い刺激で行う治療であれば、しっかり周辺の筋肉を動かし、血行を促進する事が出来れば炎症や筋緊張は軽減して症状が改善する事も珍しくありません。
弱い刺激の治療を行っている治療院は、あまり多くはないと思いますが、もしよろしければこのページで書かれている事を治療院選びの参考にして下さいね。
もしどこに相談していいか分からない、どこに相談してもダメだったという人は一度私にお気軽にご相談して下さいね。
症状によっては限界もありますが、私は脊柱管狭窄症の治療をそれなりに得意にしていますので。
以上で「脊柱管狭窄症の症状や痛む場所が移動したり変化する理由」のページの説明を終了させていただきますが、下記に脊柱管狭窄症に関連するページのリンクも載せていますので、興味のある人はそちらも是非参考にして下さいね。
おすすめ記事
スポンサーリンク
脊柱管狭窄症に関しての記事
「脊柱管狭窄症の夜の痛みに有効な楽な寝方や寝る姿勢について」
「脊柱管狭窄症で発生する症状や軽度、重症度チェックについて」
「歩けない、歩くと痛い脊柱管狭窄症の人は無理やりでもウォーキングすべき?」
「脊柱管狭窄症の人が腹筋やスクワットなどの筋トレを行うリスク」
「脊柱管狭窄症にマッサージやツボの指圧がオススメできない理由」
「猫背や前屈みはいけないのか?脊柱管狭窄症と正しい姿勢について」
「脊柱管狭窄症の人が日常生活でやってはいけない気をつける事や禁忌について」
「手足に力が入らない運動障害や筋力低下と脊柱管狭窄症との関係について」
「雨や天気、気圧の変化によって脊柱管狭窄症の症状が悪化してしまう理由」
「デスクワーク時の脊柱管狭窄症の人の椅子の座り方やクッションについて」
「サポーターやコルセットによる固定は脊柱管狭窄症に効果はあるのか?」
「肥満や体重の増加、太りすぎは脊柱管狭窄症に関係するのか?」
「足が上がらない、つま先立ちができない症状と脊柱管狭窄症との関係」
「冬の寒い日や季節の変わり目に脊柱管狭窄症の症状が悪化しやすい理由」
「脊柱管狭窄症とふくらはぎやスネの痛み痺れ、こむらがえりとの関係について」
「寝ると痛い脊柱管狭窄症の人は仰向け、横向き(側臥位)、うつ伏せ、どれが楽なのか?」
「整形外科で行われる牽引などのリハビリは脊柱管狭窄症に効果はあるのか?」
「脊柱管狭窄症の人が体や腰を反らしたり背伸びをすると痛い理由」
「年寄りや高齢者の脊柱管狭窄症は寝たきりになるリスクも大きい!?」
「脊柱管狭窄症にストレッチや体操を行うと悪化する事も多い?」
「ふらついたり頻繁に転倒しそうになる脊柱管狭窄症は要注意?」
「ブロック注射の効果を感じない脊柱管狭窄症の人はどうするべきか?」
「脊柱管狭窄症は体が熱く感じるなどの感覚障害が発生する事もある?」
「飲み込みにくいなどの嚥下障害や顔の痛みと脊柱管狭窄症との関係」
「脊柱管狭窄症を放置して悪化するとどういった症状が発生するのか?」
「くしゃみや咳など風邪や発熱によって脊柱管狭窄症が悪化する理由」
「脊柱管狭窄症の症状でまともに起き上がれない人の楽な起き上がり方」
「脊柱管狭窄症の症状で夜眠れない人向けにオススメのマットレスについて」